top of page
検索
All Posts


スマート農業は「ロボット」ではなく「経営戦略」である── 山梨県立農林大学校 講義レポートから見えた、若き農業者たちの“本質的な気づき”
先日、山梨県立農林大学校にて「有機農業及び先端技術特別講座(ICT研修)」の講師を務めました。 講義後、養成科1年の学生28名全員から提出された研修レポートを拝見し、強い手応えを感じました。そこに書かれていたのは、「新しい技術はすごい」という表層的な感想ではありません。 農業を“経営”としてどう成立させ、どう守り、どう次世代につなぐか という、本質的な問いでした。 本稿では、学生たちのレポートから浮かび上がった「次世代農業者が捉えるスマート農業のリアル」を、専門家の視点で整理します。 1. スマート農業は「ハイテク」ではなく「課題解決の手段」 講義前、多くの学生がスマート農業に対して抱いていたのは、 ロボット・AI・ドローンといった最先端技術 大規模法人向けの高コストな仕組み 自分たちにはまだ早い世界 というイメージでした。 しかし講義後のレポートでは、その認識が明確に変化しています。 「ICTは目的ではなく、課題解決のための手段」 「経営のリスクを抑え、収益を最大化するための考え方」 「自分たちの農業を説明できるようにする道具」...
Tomoyuki Watanabe
1月28日読了時間: 4分


鹿児島県主催 令和7年度「かごしまスマートファーマー育成セミナー」受講生募集
― 地域特性を踏まえたスマート農業導入と地域連携を学ぶプログラム ― 鹿児島県は、「令和7年度 スマート農業導入加速化推進事業」の一環として、「かごしまスマートファーマー育成セミナー」を2026年1月から2月にかけて開催します。本セミナーの企画・運営は、スマートアグリコンサルタンツ合同会社(代表:渡邊智之)が担当します。 本セミナーは、 農業者に加え、市町村・JA等の関係機関も対象 とし、スマート農業を単なる技術導入で終わらせるのではなく、 地域特性に即した経営改善や地域連携につなげること を目的としています。 プログラムは 各地域2回構成 で実施します。第1回は全参加者共通のオンライン講義、第2回は地域別(大隅・薩摩・種子島)に分かれ、対面形式で開催します。 ■ 第1回(全地域共通・オンライン開催) 日時:2026年1月14日(水)13:30~16:30 テーマ:全国先進事例から学ぶスマート農業の最新動向 ゲストスピーカー: 滋賀県 有限会社 フクハラファーム代表取締役 福原 悠平 様 講演テーマ: 大規模経営におけるスマート農業導入~...
Tomoyuki Watanabe
2025年12月17日読了時間: 3分
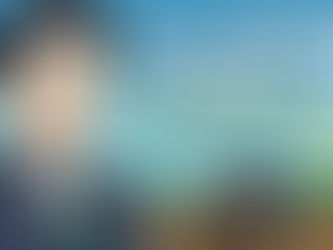

スマート農業技術活用促進法を読み解く:日本の農業OSアップデート計画
日本の農業がいよいよ本格的に“OSアップデート”のフェーズに入りました。その象徴が、2024年に施行された 「スマート農業技術活用促進法」 です。 私はこれまで農林水産省でスマート農業政策に携わり、自治体・農業法人・スタートアップと現場で伴走してきました。その視点から見ても、この法律は日本農業の構造を変えるターニングポイントになると感じています。 今回は、ポッドキャストとYouTubeでも取り上げたこの新制度の本質を、実務者にも一般の方にも伝わる形で整理していきます。 1|なぜ今「スマート農業技術活用促進法」が必要なのか 日本の農業は長年、「高齢化」「人手不足」「担い手減少」という課題を抱えてきました。しかし、政府は今回 従来とはまったく違うアプローチ を取りました。 それが 「テクノロジーを農業の標準装備にする」 という明確な方針です。 背景には、改正食料・農業・農村基本法があります。ここで初めて、 「生産性向上には先端技術活用が不可欠」 と国の基本方針に明記されました。 つまり今回の法律は、その方針を“実行に移すエンジン”。...
Tomoyuki Watanabe
2025年11月20日読了時間: 5分


行政ではもう支えきれない農村を救う、新しい伴走者。「農村プロデューサー」という希望と、私自身の学び
日本の農村は今、静かに、しかし確実に転換点を迎えています。人口減少と高齢化の進行、コミュニティの弱体化、そして行政人員の大幅な減少。これまで地域を支えてきた“人”がいなくなりつつある現実は、現場で活動していてもひしひしと感じます。 そんな危機の中で、新しい光として生まれたのが**「農村プロデューサー(農村地域プロデューサー)」です。 私は、 先日この「農村プロデューサー養成講座」を受講し、無事修了しました。 講座で得た学びは、私自身の活動に直結するものであり、今後の地域支援・プロジェクト形成にとって大きな財産になったと感じています。 今回の記事では、この講座が目指す人材像、育成設計の意味、そして私自身が受講して得た実感について深く共有します。 ■ 行政人員が激減する日本の農村 農水省の公式資料には、次のような衝撃的データが示されています。 都道府県の農林水産担当職員:15年で23.5%減 市町村の農業担当職員:27%減 行政のスリム化は避けられない流れです。その一方で、農村の抱える課題は複雑化し、より“個別の事情”を理解した伴走が必要になっていま
Tomoyuki Watanabe
2025年11月19日読了時間: 4分
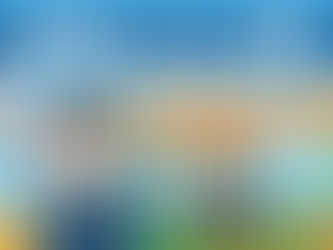

【異業種×スマート農業】参入企業が必ず知るべき“成功の方程式”とは?
「うちの技術、絶対に農業に役立つはずなのに、なぜか農家さんには刺さらない…」 スマート農業に参入した異業種企業の方から、私はこれを何度も聞いてきました。素晴らしい技術があるのに手応えがない。問い合わせはそこそこあるのに、導入までなかなか進まない。その裏側には、 技術力だけでは超えられない“深い溝” が横たわっています。 1. なぜ今スマート農業がこんなに注目されているのか まず、大前提となる日本の現状から。 2020年時点で、農業に従事している人の 約7割(69.6%)が65歳以上 です。この数字が意味しているのは、 一人あたりの作業負担が増え続けること ベテラン農家の「勘」「経験」「さじ加減」といった暗黙知が、引退とともに急速に失われつつあること という、かなり切実な構造的問題です。 この課題を解決する手段として期待されているのが「スマート農業」です。ドローンによる農薬散布、AIによる自動収穫、無人トラクター、環境センサー…農業と先端技術を掛け合わせることで、 省力化(労働力不足の補完) 技術継承(暗黙知の見える化・標準化) を同時に実現しよ
Tomoyuki Watanabe
2025年11月14日読了時間: 8分


なぜクマ被害が過去最多に?―複合要因を解剖し「共存」を現実解にする
2025年、全国でクマの出没・被害がかつてないペースで報告されています。10月末の時点で死亡事故は過去最多の9人。人身被害の件数も、統計開始以来の最悪水準。「山の話」ではなく、いまや私たちの 生活圏のすぐそば で起きている現実です。 1. 何が起きているのか ― “人里”で増えるクマの出没 これまで山奥に限られていたはずのクマ被害が、近年では 住宅地や農地、商業施設 など、日常の延長線上で発生しています。農林水産省の統計によれば、令和5年度のクマによる農作物被害額は 約7億円 。リンゴ、柿、栗、トウモロコシ、そして養蜂場――いずれも秋の味覚が被害の中心です。 特に東北地方や北陸では、秋(9〜11月)に被害が集中。冬眠前の食料不足と、生活圏への進出が重なり、危険が高まっています。 2. なぜ今クマが増えているのか ― 四つの複合要因 単一の原因ではなく、複数の要素が重なり合う「複合危機」です。 (1)生息環境の変化 中山間地域の 過疎化・高齢化 が進み、耕作放棄地や放置果樹が増加。里山の“人の手”が入らなくなった結果、クマが隠れやすく、餌を得やすい
Tomoyuki Watanabe
2025年11月10日読了時間: 4分


お米券だけじゃない──鈴木憲和大臣が見据える「スマート農業と食料政策の転換点」
はじめに こんにちは。今、日本の農政をめぐって静かに、そして熱く議論が起きています。きっかけは――“お米券”。 一見、福祉政策の話のように見えるこの新制度案。でもその背景には、 日本の農政を根本から見直そうとする動き が隠れています。そしてその中心にいるのが、43歳の若き農林水産大臣、 鈴木憲和さん です。 私はスマート農業の現場支援と政策提言の両面に関わってきました。かつて農林水産省で働いた経験から見ても、鈴木大臣の打ち出した方向性は、 「食料安全保障」と「スマート農業」を結びつける転換点 になり得ると感じています。 お米券をめぐる議論が示す“農政の深層構造” お米券構想は、「お米価格の高騰」に対応する支援策として発表されました。しかし単なる消費者支援ではなく、 米の市場価格を維持しながら、困窮層にはクーポンで支援する という二層構造を採っています。 つまり、 農家の生産意欲を削がず、 消費者への負担を軽減する、というきわめて繊細な政策バランスを取ろうとしているわけです。 SNSでは「現金の方がいい」「お米に限定するのは不公平」と賛否両論が巻き
Tomoyuki Watanabe
2025年10月30日読了時間: 4分


令和7年度から本格始動 ― 「中山間地域等直接支払制度」に見るスマート農業導入の新潮流― テクノロジーで“守る農業”から、“挑む農業”へ ―
■ はじめに 日本の農業の原風景ともいえる中山間地域の棚田や傾斜地。これらを維持するための「中山間地域等直接支払制度」が、 令和7年度(2025年度)から第6期対策として大きく刷新 されました。 単なる「農地維持の補助金」から、 地域経営・スマート農業を軸にした未来型支援制度 へ──。本記事では、その全貌と現場へのインパクトを、制度設計と技術導入の両面から専門的に解説します。 ■ 制度の目的 ― 「守る」から「稼ぐ」へと変わる文脈 中山間地域は、地形的な制約により大規模化が難しく、生産コストが高い地域です。国はこの「不利を補正」し、 農地8.4万ヘクタール(東京ドーム約1.8万個分)の減少防止 を5年間の目標に掲げています。 従来は「農地を守る活動」に対して交付する仕組みでしたが、今回の第6期では、 地域間連携(ネットワーク化)とスマート農業技術の導入 という「攻めの2本柱」が加わりました。 ■ 新設された2つの加算措置のポイント ① ネットワーク化加算 複数の集落が連携・統合して営農体制を強化 する取組を支援 10aあたり最大1万円(上限100
Tomoyuki Watanabe
2025年10月19日読了時間: 4分


自律型除草ロボットが切り拓くスマート農業の次世代フェーズ
―補助金制度、導入事例、普及の壁を徹底解説― ■ 「除草」が抱える構造的課題 農業現場で最も“見えにくく、かつ重い”負担の一つが除草です。農林水産省や農研機構の分析によれば、除草作業は年間総労働時間の15〜25%を占め、1haあたり200〜300人時を費やすこともあります。 とくに中山間地や果樹園では、傾斜・樹間・支柱といった制約が機械化を阻み、「安全に・効率的に・薬剤に頼らず草を抑える」手段の確立が長年の課題でした。 ■ 政策が後押しする“省力化×安全×環境”の投資領域 2024年10月に施行された「スマート農業技術活用促進法」により、ロボット除草のような省力・安全・環境調和技術は、国の恒常支援対象として制度化されました。 主な支援スキームは以下の3層です。 制度 内容 補助・優遇 スマート農業技術活用促進法(新法) 生産方式革新・開発供給の2認定を通じ、税制・金融優遇 認定でJFC長期低利資金、補助事業加点 スマート農業・農業支援サービス導入総合サポート 導入・実証・事業化を一体支援 補助1/2、先進モデル加点 農地利用効率化等支援交付金 ロ
Tomoyuki Watanabe
2025年10月16日読了時間: 4分


植物工場市場の最新トレンドと今後の展望
―高付加価値化・自動化・データ統合が鍵― 植物工場(完全閉鎖型)や次世代施設園芸は、「生産性向上」「付加価値創出」「環境負荷低減」という日本農業の目指す方向性と合致し、持続的な発展が期待されています。しかし、公開情報でも約半数が赤字とされるように、ユニットエコノミクス(UE...
Tomoyuki Watanabe
2025年9月28日読了時間: 3分


東北大学 大学院生からのヒアリングで考えた農業DXの方向性
先日、修士論文研究の一環として、東北大学の大学院生からヒアリングを受ける機会がありました。普段は私自身が農業者や行政・企業に対してヒアリングを行う立場ですが、今回は逆に質問を受ける側として、農業DXに関する取り組みや課題を整理する貴重な時間となりました。...
Tomoyuki Watanabe
2025年9月21日読了時間: 5分


「農業死亡事故の実態と構造的課題──スマート農業が果たす安全保障機能」
はじめに 農林水産省の統計によれば、2017年の農作業事故死亡者数は304人。就業者10万人当たりに換算すると16.7人で、他産業を大きく上回る“異常値”です。これは日本の農業が抱える構造的リスクを如実に示しています。農業は自然条件に依存するがゆえに時間的・心理的な制約が大...
Tomoyuki Watanabe
2025年9月16日読了時間: 3分


🌱 スマート農業:日本の6000億円市場への参入ガイド
農業が抱える課題とスマート農業の可能性 日本の農業は高齢化と担い手不足が深刻です。農業従事者の約7割が65歳以上で、作業面積の拡大や人手不足が進行しています。こうした課題を解決する手段として注目されているのが、 ITを軸とした先端技術を組み合わせた「スマート農業」です。ドロ...
Tomoyuki Watanabe
2025年9月15日読了時間: 2分


🌏 世界の農業ルールづくりに参画 ― ISO/TC347と日本の挑戦
1. ISO/TC347とは何か? 2023年10月にISO(国際標準化機構)に設立された ISO/TC347(データ駆動型アグリフードシステム) は、農業から食品消費までのサプライチェーン全体を対象に、 データに基づいた意思決定を可能にする国際規格 を策定する場です。...
Tomoyuki Watanabe
2025年9月14日読了時間: 3分


経験と勘を「見える化」するスマート農業の最前線
――岡山の白桃から稲作まで広がるDXの実装 ■ はじめに 農業の現場では、長年にわたり「経験と勘」が収穫や栽培管理の成否を分けてきました。しかし、担い手不足・高齢化が進む中、その知見を次世代に引き継ぐのは容易ではありません。そこで注目されているのが、ICTやロボットを活用し...
Tomoyuki Watanabe
2025年9月12日読了時間: 3分


スマート農業の落とし穴? ― 「ロボット導入で売上が下がる」現象をどう捉えるか(記事考察)
ロボット導入で、なぜ売り上げや作付け面積が減るのか? スマート農業が抱える意外な落とし穴とは | Japan Innovation Review powered by JBpress 本稿は、上記の山口亮子氏の記事「ロボット導入で、なぜ売り上げや作付け面積が減るのか?」(...
Tomoyuki Watanabe
2025年9月1日読了時間: 5分


猛暑の農業と「きこりのジレンマ」──スマート農業は“斧を研ぐ時間”になれるか?
猛暑に挑む農家の現実 スマート農業の導入が進まない深層 | Forbes JAPAN 公式サイト(フォーブス ジャパン) 上記Forbes JAPANの記事を読みながら、私は「きこりのジレンマ」という寓話を思い出しました。...
Tomoyuki Watanabe
2025年8月18日読了時間: 3分


なぜ7割の農家がスマート農業に動けないのか?―猛暑・人手不足・情報格差のリアル
こんにちは。スマート農業を専門に全国の現場と向き合っている渡邊智之です。 2025年の夏、日本の農業は再び極限状態に置かれています。炎天下での作業に加え、高温障害、収量減、品質低下、獣害など、「農業経営の不確実性」が極限まで高まる中、注目されるのが「スマート農業」です。...
Tomoyuki Watanabe
2025年7月30日読了時間: 3分


スマート農業による「省力化投資」の最前線──国が描く2030年への変革ロードマップ
こんにちは。スマートアグリエバンジェリストの渡邊智之です。 2025年6月、農林水産省は「省力化投資促進プラン(農業)」を発表しました。 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/shouryokukatou...
Tomoyuki Watanabe
2025年7月17日読了時間: 3分


稼げる農業の新基準──舞台ファームが切り拓く「農エネ業」の未来
こんにちは。スマートアグリエバンジェリストの渡邊智之です。今回は、仙台発の農業法人「舞台ファーム」が提示した未来志向の農業戦略について、専門家の視点から掘り下げていきたいと思います。 ■ 舞台ファームの挑戦:農業の経営ノウハウを“外販”するという発想...
Tomoyuki Watanabe
2025年7月15日読了時間: 4分
bottom of page



